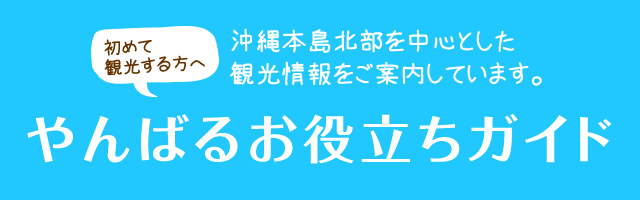【掲載料金について】当サイトに掲載している料金には増税前のものがあります。順次更新しますが、正しい料金は各施設へお問い合わせください。
ホーム > やんばるお役立ちガイド > 沖縄のことば(用語)
沖縄のことば(用語)
ちょっと知っていると役に立つ沖縄の用語・方言、読みかたなどを集めました。現地に行く前の参考にしてください。
食べもの
-
ウージ
さとうきび
-
沖縄そば、ソーキそば
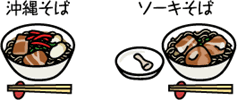 沖縄そばは豚の三枚肉(バラ肉)がそばの上にのっており、ソーキそばは豚のソーキ肉(アバラ骨付の肉)がのっています。通常、使われているそばは同じですが、お店によってそばの味も肉の味付けも異なります。
沖縄そばは豚の三枚肉(バラ肉)がそばの上にのっており、ソーキそばは豚のソーキ肉(アバラ骨付の肉)がのっています。通常、使われているそばは同じですが、お店によってそばの味も肉の味付けも異なります。
-
サーターアンダギー
沖縄風のドーナッツ。「サーター」は砂糖、「アンダギー」は揚げ物のことです。小麦粉、砂糖、卵を合わせて練った生地を丸めて油で揚げて作ります。
-
ジービン
つるむらさきのこと。湯どおししておひたしに。油との相性も良いので炒め物や揚げ物にも向いています。
-
ジューシー
 沖縄風の炊き込みご飯。豚肉とにんじん、椎茸、昆布などの野菜を、だし汁や調味料とともに炊き込んだご飯です。
沖縄風の炊き込みご飯。豚肉とにんじん、椎茸、昆布などの野菜を、だし汁や調味料とともに炊き込んだご飯です。
-
チャンプルー
「チャンプルー」は焼いた島豆腐と季節野菜の炒め物のこと。
※参照「農林水産省 うちの郷土料理」 -
鬼餅(ムーチー)
もち米に黒糖や白糖を加えたものを月桃(サンニン)の葉で包んで蒸したお餅。沖縄では旧暦の12月8日(新暦だと1月15日)に食べて、子供の健康を願う習わしがあります。
-
ミミガー
豚の耳の皮。ピーナッツバターや酢醤油で和えるのが一般的です。
-
ラフテー
豚の角煮のこと。
-
海ぶどう
緑色の小さい粒々がついた海草で、プチプチとした食感とほどよい塩味が特徴です。ご飯に海ぶどうをたっぷりのせた「海ぶどう丼」も人気が高いメニューです。
-
ちんすこう
沖縄を代表する伝統菓子で、ラード、小麦粉と砂糖をこね合わせて焼き上げます。クッキーのようなサクッとした歯触りが特徴です。
-
黒糖
原料のサトウキビから精製しないで作られる砂糖。沖縄ではお茶受けとしても家庭に常備され、カステラやちんすこうなどのお菓子にも使われています。
-
泡盛
琉球王国の時代から続く伝統的な蒸留酒で、発酵に黒麹菌、原料にタイ米を使って作られます。3年以上熟成させた泡盛を古酒(くーす)といい、沖縄料理との相性も抜群です。
-
さんぴん茶
茶葉に白い小さなジャスミンの花が入っているお茶。ジャスミン茶を指す中国語「香片茶(シャンピェンツァ)」から転じたもので、ふわっとした花の香りが楽しめます。
-
ブクブク茶
大きな木鉢に煎った米を硬水で煮出した湯と、さんぴん茶と番茶を混ぜた茶湯を入れ、茶せんで泡を立てます。ソフトクリームのように盛り上げた泡をさんぴん茶にのせ、仕上げに刻んだピーナッツをのせていただく伝統的なお茶です。
-
シークヮーサー
やんばるに自生する柑橘類で、沖縄の方言でシーは「酸っぱい」、クヮーサーは「食べさせる」という意味。絞った果汁をジュースに加工したり、ポン酢などお料理にも使われます。
地名、地域、土地に関することば
-
アシビナー
遊び場、地域の行事などを行う広場のこと
-
ウチナー
沖縄
-
ウチナーンチュ
沖縄の人のこと。
-
バンコ
八重山地方の言葉で、暑苦しい夏に風通しの良い木陰や樹の上に板を渡して、そこで昼寝や情報交換をした場所のことをいいます
-
ヒンプン
なかがき。門と母屋の間の垣で、魔物除けとされている。
-
ヤー
家のこと。掘った小屋はアナヤー、カヤぶきの家はカヤブチヤー
-
ヤールー
守宮(やもり)のこと。家の守り神と呼ばれ、よく鳴く“ヤールー”が住む家にはお金が入るといわれてます
-
山原(ヤンバル)
 「山原」と書いて「やんばる」と読む。北部全体を指すこともあれば、国頭村、大宣味村、東村のあたりや、そこに広がる森林を指すこともあります。
「山原」と書いて「やんばる」と読む。北部全体を指すこともあれば、国頭村、大宣味村、東村のあたりや、そこに広がる森林を指すこともあります。
-
大宜味村
「おおぎみそん」。シークヮーサーやマンゴーで有名です。
-
恩納村
「おんなそん」
-
宜野座村
「ぎのざそん」。阪神タイガース一軍のキャンプ地があります。
-
国頭村
「くにがみそん」
-
今帰仁村
「なきじんそん」。世界遺産の今帰仁城跡があります。
-
東村
「ひがしそん」
-
本部町
「もとぶちょう」。沖縄美ら海水族館(海洋博記念公園)があります。
その他
-
アッチャー
歩く人。ウミアッチャーは漁師。通うという意味で職業を表現する場合もあります。
-
ウミンチュ
漁師(海人)
-
うりずん
旧暦の2、3月頃を指します。3~4月頃の植え付けにほどよい雨が降る季節の意味になります。
-
カリユシ
めでたいこと。かりゆしウェアは沖縄で着用される沖縄特有のシャツのことでお土産にもなります
-
キジムナー
ガジュマルの木に宿る子供の木の精のこと
-
三線(サンシン)
三味線のこと。蛇の皮を張ってあるのが特徴です
-
ちむどんどん
ちむ(肝=気持ち・心)が高鳴る、わくわくする、ドキドキする様子
-
チュラカーギ
美人
-
ユンタク、ユンター
おしゃべり
※諸説あります